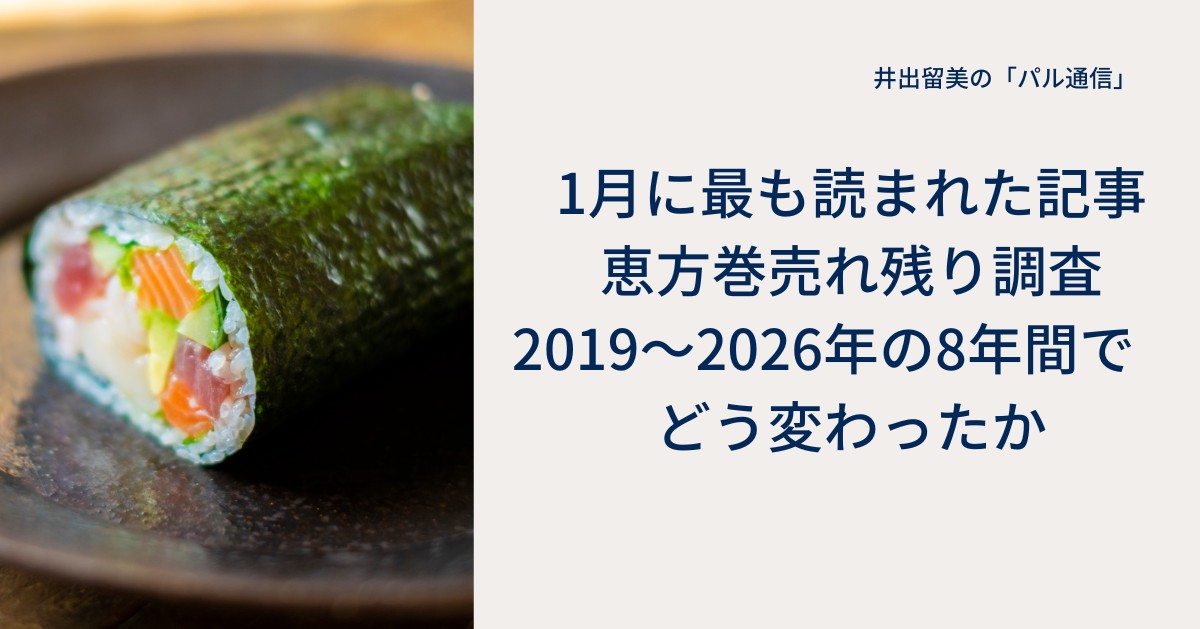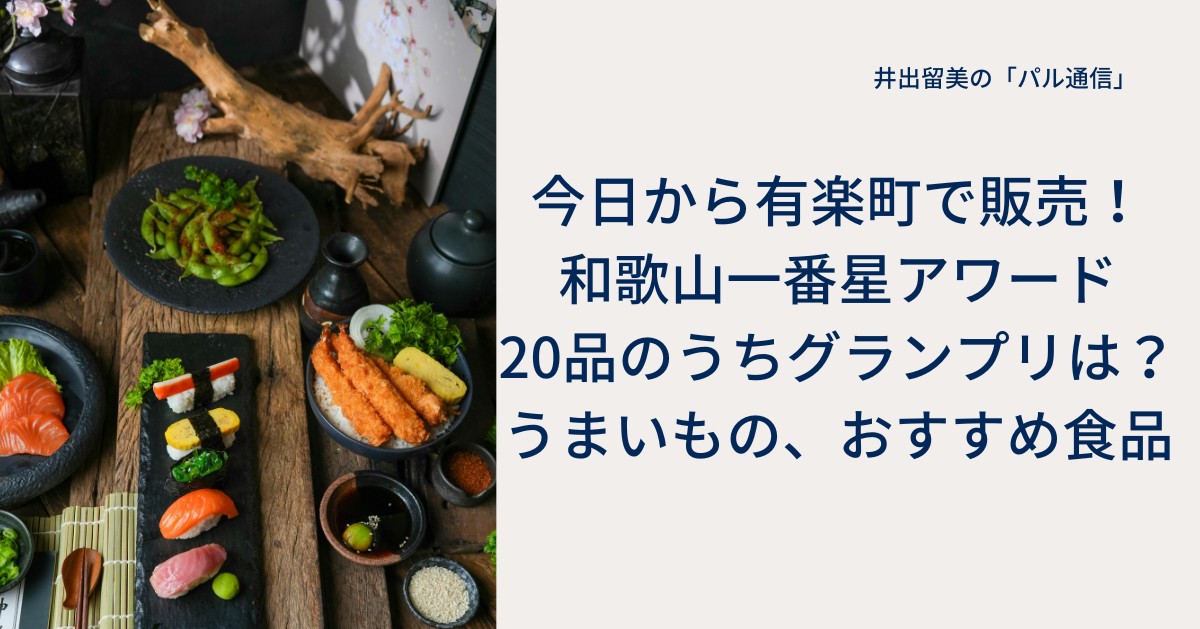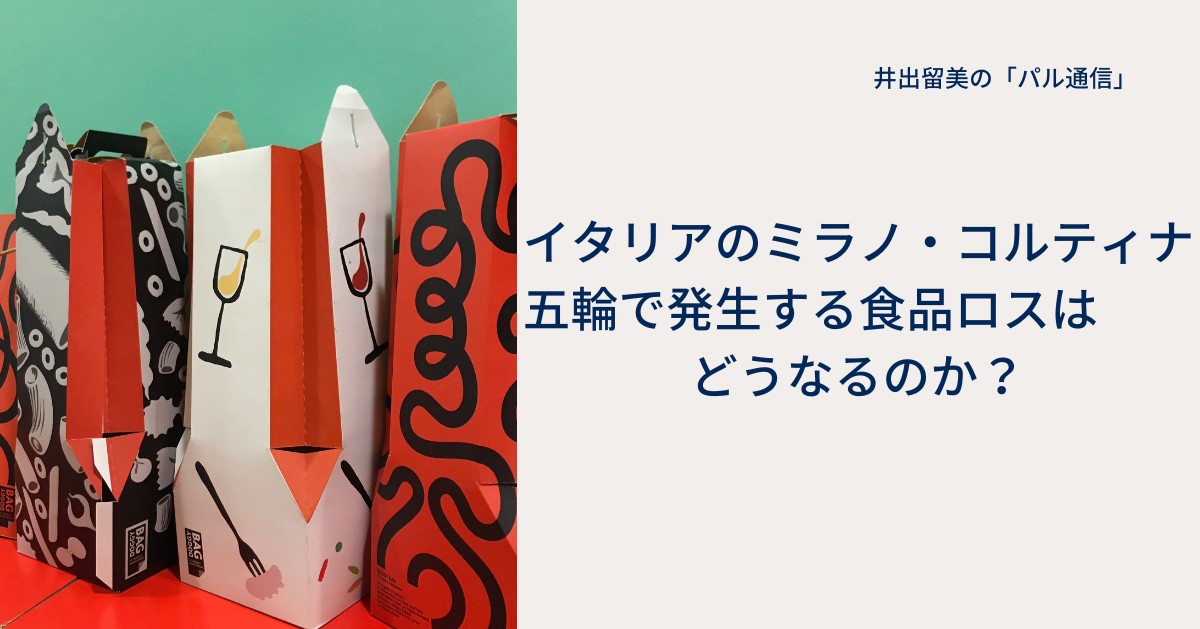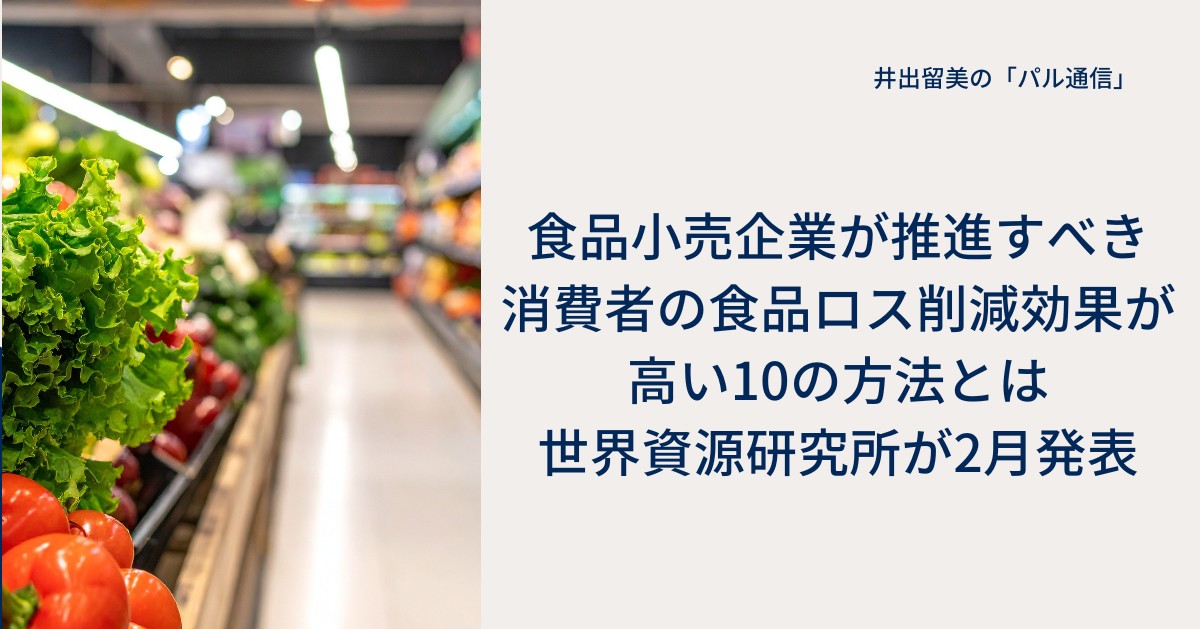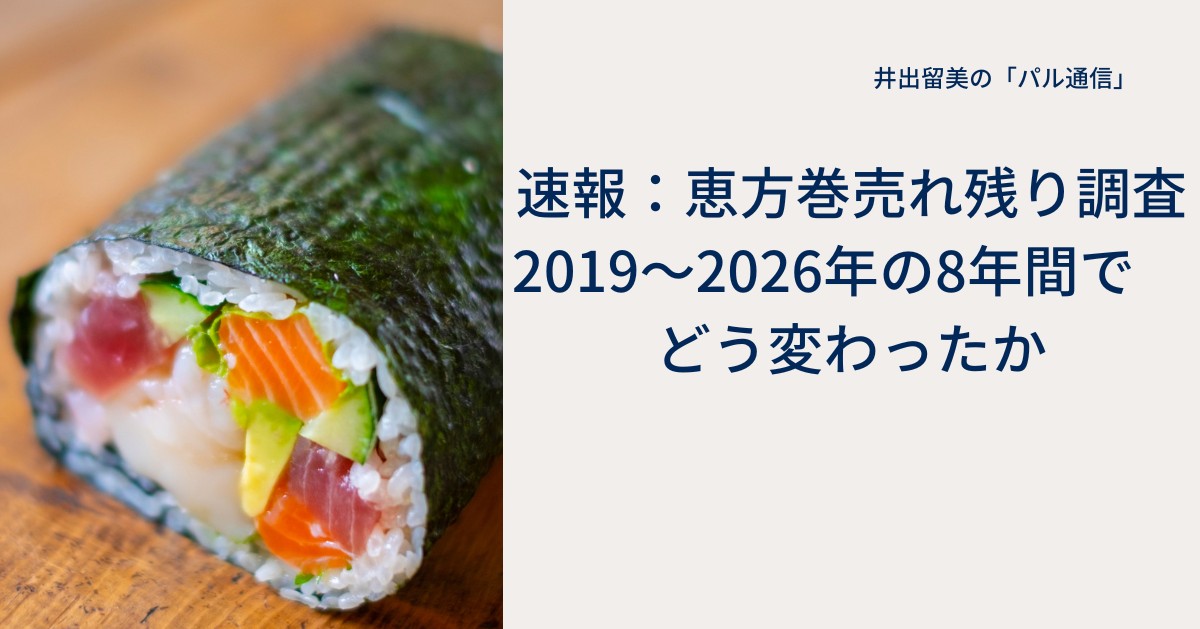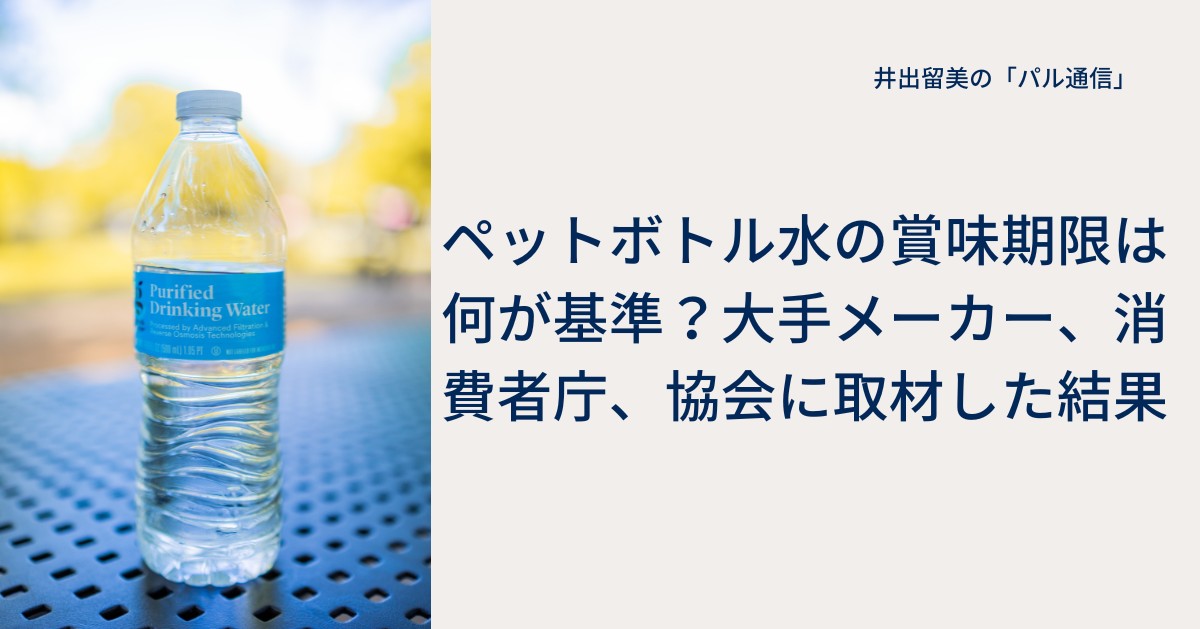世界に誇れる、我が国のエコフィードに関する取組
こんにちは。ニュースレター「パル通信」に登録いただき、食品ロス削減やサステイナビリティの活動をサポートいただき、ありがとうございます。今回は178号をお届けします。
今回のニュースレター「パル通信」では、宮崎大学農学部を2024年3月に退官された川島知之先生に、食品残さを活用するエコフィードについてご寄稿いただきます。
お知らせ:来月6月28日(金)19時より、サポートメンバーの方限定の対面で第9回交流会を開催します。ニューヨークからYAMMA(ヤンマ)デザイナーの山崎(やまさき)ナナさん、当日帰国して参加されます!ほか、theLetter編集部の濱本至さん、日本ハムの宮本雅宏さん。ハローズの太田光一さんは岡山から交流会のために上京して下さるそうです。ご参加希望の方は返信でお知らせください。また6月30日(日)午前9:30-10:30にはオンラインで、第10回交流会を開催します。県庁職員の方よりお米を題材としたお話をいただき、スーパーで米が精米1ヶ月で捨てられる現状をどう変えていくかについて、参加者で現状や解決策を話したいと思います。聴くだけ参加も歓迎します。
川島知之先生プロフィール
家畜の飼料学、特にエコフィードを専門とし、畜産分野からの温室効果ガス削減も研究対象としてきました。農研機構畜産草地研究所、国際農林水産業研究センター等に勤務し、2015年から宮崎大学農学部畜産草地科学科教授になり、2024年3月末に定年退職しました。4月以降は現場に近いところで働こうと、日本で一番リサイクル率が高い鹿児島県大崎町を中心に、コンサルタント的な立場で仕事を始めようとしているところです。
パル通信の読者におかれましては、エコフィードとは何かご存じの方も多いと思います。私、川島知之は、2001年、食品リサイクル法が施行された年から、エコフィードをライフワークとしてきました。海外でもエコフィードという言葉が使われるようになるほど、その取組は海外からも認められるようになってきました。
我が国のエコフィードの取組
食品残さは古くから飼料として利用されてきました。1950年代からの高度経済成長期、急速畜産物の需要が伸び、それに対応するために能力の高い外来種が導入されました。飼養管理を支えるために配合飼料が使われるようになり、食品残さを飼料として利用することは少なくなりました。しかし、食品リサイクル法が2001年に制定されてから、食品残さの飼料化が再び注目されるようになりました。
エコフィードとは、食品製造副産物、余剰食品、調理残さなどを利用して調製された家畜用飼料を指します。それまでは食品残さ飼料、リサイクル飼料、食品循環資源利用飼料等と呼ばれていましたが、農林水産省が支援する事業において、普及につなげるために魅力的な名前にしようと定められたものです。
私は、2001年4月に、農水省傘下の研究独法である畜産草地研究所で、エコフィードを推進するために新設された飼料評価研究室の室長となり、オールジャパンの活動を推進する立場になりました。その普及・啓発のため、エコフィードに関する全国シンポを2003年から年1回程度開催しました。参加者がどんどん増え、2006年1月のシンポには468名の参加者がありました。当時、畜産草地研究所が主催する会議では、破格に多い参加者でした。当時はトウモロコシの国際価格が高騰するとともに、食品リサイクル法でも飼料化を優先することが決まるなど、エコフィードが注目され、その生産量が大きく伸びた時期でした。現在、エコフィードの生産量は伸び悩んでいます。エコフィードに仕向けられる原料が枯渇してきたからか、あるいは、エコフィードを取り巻く社会環境が変わってきたからか。今年度、このことを調査する予定です。

2006年のエコフィード全国シンポの様子です。民間からの参加も多く、盛大でした(提供:川島知之)
ヨーロッパでの取組
エコフィードの取組は順風満帆に進捗してきた訳ではありません。最大のピンチは、食品リサイクル法が制定された2001年10月に国内で初めてBSE(牛海綿状脳症)が発生したことです。それによっては、飼料安全法が改正され、反芻家畜への動物性タンパク質の利用が厳しく制限されました。しかし、幸いなことに、豚や鶏用の飼料としては、食品残さはもともと食用であり、食料自給率の向上、食品廃棄物の排出の軽減・再利用を通じた循環社会実現といった公益の推進に特に寄与するので、適切に加熱処理すれば肉を含むエコフィードも引き続き飼料として利用できることになりました。
一方、ヨーロッパでは全く異なる対応がとられました。EU では 1980 年代後半以降の BSE による甚大な被害に加え、口蹄疫や豚熱の防除のため、肉を含むエコフィードについて、牛のみならず、豚や鶏に対しても飼料利用を禁止する規則(Feed Banと呼びます)が 2002 年に定められました。加熱殺菌を徹底して、豚用飼料として安全に利用されていたドイツやオーストリアでは特別に猶予期間が設定されましたが、2006 年にはヨーロッパ全体で利用が禁止されました。そのため、ヨーロッパでは、20年近く、肉を含むエコフィードは利用されていません。日本の取組とは大きく異なる状況にあります。

2004年に訪問したドイツのエコフィード製造工場 ドイツでは2000年当時、職品残さを加熱処理後リキッド飼料として養豚家に販売する業者が430社もあったそうです。Feed Ban施行後はそれらの残さの大部分はバイオガスに仕向けられています(提供:川島知之)

エコフィード製造工場にあったポスターです。食品残さを加熱処理する前と後で交差汚染しないよう、きちんと管理していることがわかりやすく説明されていました(提供:川島知之)
ヨーロッパで貴重な飼料資源が失われている状況を憂う人が出てきました。イギリスのジャーナリスト、トリストラム・スチュアート氏です。彼は2008年に私の研究室に来てくれて、エコフィードに関する取材をしてくれました。そして、2009年にWaste: Uncovering the Global Food Scandalという本を出版しています(日本語訳は2010年世界の食料・ムダ捨て事情(NHK出版)として出版されました)。その中で、日本でのエコフィードの取組のことを丁寧に紹介し、食品廃棄物はまず家畜飼料として利用し、その糞尿からバイオガスを生産し、消化液を施肥するという、カスケード利用が重要であり、そうでなければ食品廃棄物が有する潜在能力を無駄にすることになるという、私の説明もきちんと書いてくれました。彼は2011年に、国際的な環境や開発援助に対するソフィー賞を受賞しています。

トリストラム・スチュアート氏の著書 世界の食料・ムダ捨て事情(NHK出版)(川島知之提供)
その後、持続可能な開発目標(SDGs)が 2015 年に国連総会で採択され、食品ロス削減が目標の一つとなりました。ヨーロッパでも食品ロス削減の取組が盛んになり、EU の予算による、食品ロス削減に関する研究プロジェクト、REFRESH(1) が2015年から4か年実施されました。前述のトリストラム・スチュアート氏もこのプロジェクト設立に深く関わっています。食品ロス削減に向けてエコフィードも取り上げており、私はこのプロジェクトに 2018 年と 2019 年の 2 回招聘され、日本でのエコフィードの取組を紹介するとともに、肉を含むエコフィード利用に関する技術ガイドライン作成に協力しました(2)。日本フードエコロジーセンター(3)の事例や、日本におけるエコフィードに関する統計を参考に、日本のエコフィードの取組をイギリスやフランス全体で実施した場合の経済性や環境影響の評価結果等も示し、インパクトの大きさを解説しています。
日本ではエコフィードを製造する際、不正を働くこと(Fraud)はないかと質問を受けました。私は日本人であることを誇りに思っていますと回答したところ、妙に納得されました。
米国
一般社団法人食品ロス・リボーンセンター(4)が実施しているエコフィード関連事業の中で、エコフィードと食育についての取組を行っています。その一環として、三重県の明野高校の生徒たちの、エコフィードで黒豚を生産し、その豚肉をブランド化して販売するという取組について、日米学生会議の場で、明野高校の現役高校生と卒業生に報告していただきました。日米学生会議は、1934年から続く日本最古の国際学生交流団体で、日米両国の学生が集まり、1か月ほどの共同生活を通して、様々な世界的問題に関する議論を行うものです。私からも日本のエコフィードに関する取組について、「いただきます」と「もったいない」という日本語の意味をキーワードと話をさせていただきました。相互理解を深める前提として、両国間に存在する、社会・自然環境の違いを理解することは重要です。資源の豊かさという点で両国間の違いは歴然としており、米国の学生にとってエコフィードは全く馴染みのないものだったと思われます。米国の学生からたくさんの質問が寄せられ、エコフィードが日米学生間の相互理解醸成に貢献していることを実感しました。

日米学生会議での明野高校OBと現役学生のエコフィードに関する発表の様子(著者・川島知之が関係者より入手して提供)

日米学生会議での発表後、米国の学生たちに質問をうける明野高校OBと現役学生(著者・川島知之が関係者より入手して提供)
資料資源が豊かで、わざわざ食品ロスを飼料に利用するような面倒なことを米国では考えないだろう、そして、それを推進する研究者はいないだろうと勝手に思っておりました。
ところが先日、井出留美さんから、ミネソタ大学のジェリー・シュルソン教授が「日本はfood wasteを飼料生産にするパイオニア」と語っているという記事(5)を紹介いただきました。
さっそく調べてみると、彼が執筆している学術論文でも日本のエコフィードの取組を詳細に報告(6)していましたし、オンラインの国際会議(7)も最近開催していたことを知りました。今後の交流が楽しみです。
海外との連携
このように日本のエコフィードに関する取組は世界から注目されています。昨今の円安が示すように、日本の価値が失われているような感覚を持ってしまいがちですが、エコフィードの取組は世界に誇れるものです。
前述のREFRESHが発表したガイドラインの効果は大きく、それを読んだ、ドミニカ共和国、パナマ、コロンビア、イラク、インドの方々から、エコフィードを推進したいので、協力してほしいというメールをいただきました。新型コロナの問題もあり、これまで具体的な対応できていませんでした。私は今年3月末で大学を定年退職して、自由に動けるようになりました。今後は海外でのエコフィードについても、何らかの形で支援していきたいところです。
関連HTML
以上、川島知之先生の寄稿、いかがでしたでしょうか。
私は2022年12月、宮崎県フードバンク協議会設立記念講演会で宮崎へ行ったとき、宮崎大学農学部まで行きました。川島先生は、当時、宮崎大学のキャンパスにいらっしゃったのですね。イギリスのジャーナリスト、トリストラム・スチュアートには、私も2017年に現地で会いました。2022年10月18日に配信した『「食品ロス削減、できなければボーナス無し」のスーパーとは?』で、トリストラム・スチュアートと一緒に撮った写真を載せています。ご覧ください。
川島先生が紹介している、一般社団法人食品ロス・リボーンセンターの公式サイトに「エコフィードの普及」という項目があります。また、川島先生が、日本フードエコロジーセンターの高橋巧一さんと一緒に取り組んでいる事業で、年度末に執筆した記事は「令和5年度事業」の報告書でお読みいただけます。関心のある方はダウンロードしてお読みください。
今日の書籍
川島知之先生が寄稿文の中で紹介されていた本です。トリストラム・スチュアートが執筆し、日本語版は2010年12月に初版が発行されました。私は翌年2011年の東日本大震災での食料支援をきっかけに食品メーカーの広報室長を辞め、フードバンクの広報責任者になりました。この時、この本を購入したと思います。2011年当時、日本では「フードバンク?なにそれ、銀行?」「フードドライブ?ドライブって車?」というレベルでしたので、この本も、知る人ぞ知る存在でした。雑誌の『ソトコト』から依頼されて、本を5冊紹介してほしい、と言われた際、この本を紹介しました。
川島先生は、この本のp290とp301で紹介されています。また、日本フードエコロジーセンターの高橋巧一さんは、p295からp299にかけて紹介されています。この本は、版元では品切れになっており、インターネット書店にはまだ残っているようです。購入希望の方はお早めがよさそうです。
今日の映画
監督:石川淳一
出演:間宮祥太朗、佐藤二朗、ほか
10代に絶大な人気というこの映画。観客動員数328万人、興行収入41億円。映画のもとになったYouTube動画は2,000万回以上再生されたそうです。動画制作者の雨穴(うけつ)氏が、その後、小説として仕上げ、本も売れています。
ある一軒家の間取り図に不可解さを覚えた、オカルト動画クリエーター(間宮祥太朗)。彼が、設計士の栗原(佐藤二朗)とともに、その不可解な謎に迫っていく・・・というストーリーです。口コミでは、「佐藤二朗がハマり役」とのこと。確かに、彼の個性の強さがこの役柄にぴったりはまっています。映画評論家の吉田伊知郎さんは、佐藤二朗さんの『四角い顔が渥美清に似ている』とキネマ旬報のサイトで評しています。個人的には佐藤二朗さんの芝居を初めて観たのがよかった。また、端正な顔立ちの間宮祥太朗さんも「カッコイイ!」と人気みたいです。しかし、パル通信176号で紹介した『アニマル』のような映画こそ、10代には観てもらいたいですけどね....(パル通信を読んで、「この映画を友人と観に行くことに決めました、ユナイテッドピープルのメールマガジンも登録しました」と、サポートメンバーの方から教えていただきました。ありがとうございます!)
編集後記
パル通信サポートメンバーで日本ハム勤務の宮本雅宏さんの論文が、繊維製品消費科学会誌 「繊維製品消費科学」に掲載されました。「SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けての消費を考える」「食品ロスの削減に向けての商慣習の見直しと施策パッケージ」という内容です。8ページにわたってまとめられています。素晴らしいですね。
長野県飯田市で2023年に講演したとき、「生ごみ出しません袋」を提案しました。市民が、ごみ袋に生ごみを入れないことを約束する場合、通常は有料のごみ袋を、自治体が無償で提供します、というものです。市民にとってはごみ袋代が節約できるので食品ロスやごみを減らそうというモチベーションにつながります。自治体にとっては水分が80%を占める生ごみを劇的に減らすことにつながります。長野県上田市や須坂市ではすでに毎年継続して実践されており、効果が出ているようで、飯田市でもやったらどうかなと思った次第でした。講演を飯田市の佐藤健市長が聴いていてくださり、なんと実現が決定しました!今年8月から実施するそうです。飯田市には2018年にも講演に呼んでいただいており、その後、食品ロス削減に関する市民運動が活発になったとして、2023年にもあらためて講演に呼んでいただいていました。講演や記事で情報発信した後、どんなふうに変化したかを報告していただけるととてもうれしく、活動の励みになります。ありがとうございます!
奈良蔦屋書店でのトークイベント、無事終了しました。おてらおやつクラブや啓林堂書店の方、おてんとさん(NPO)や、ならコープの方などに集まっていただき、とてもうれしい会でした。あさって15日は、ニューヨークから帰国中の方が会いに来てくださるので、行きつけの手打ち蕎麦屋へお連れする予定です。5月28日には農林水産省ASEAN事業の一環で、フィリピンのビサヤ大学へ向けて食品ロスと気候変動の関連性について講演します(英語、45分間+Q&A15分間)。
5月17日・18日、東京の丸の内で、徳島県上勝町に関するイベントが開催されます。私も18日の夕方に行ってみようと思っています。5月下旬には神奈川県鎌倉市で「ごみフェス」が開催されます。25日は一般参加可能ですので、午後に行ってみようと考えています。関心のある方、まずはサイトの情報を見てみてくださいね。
2024年5月13日
井出留美
・サステナビリティ情報も配信中
・過去の記事も読み放題
・毎週届き、いつでも配信停止可能
・読みやすいデザイン
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績