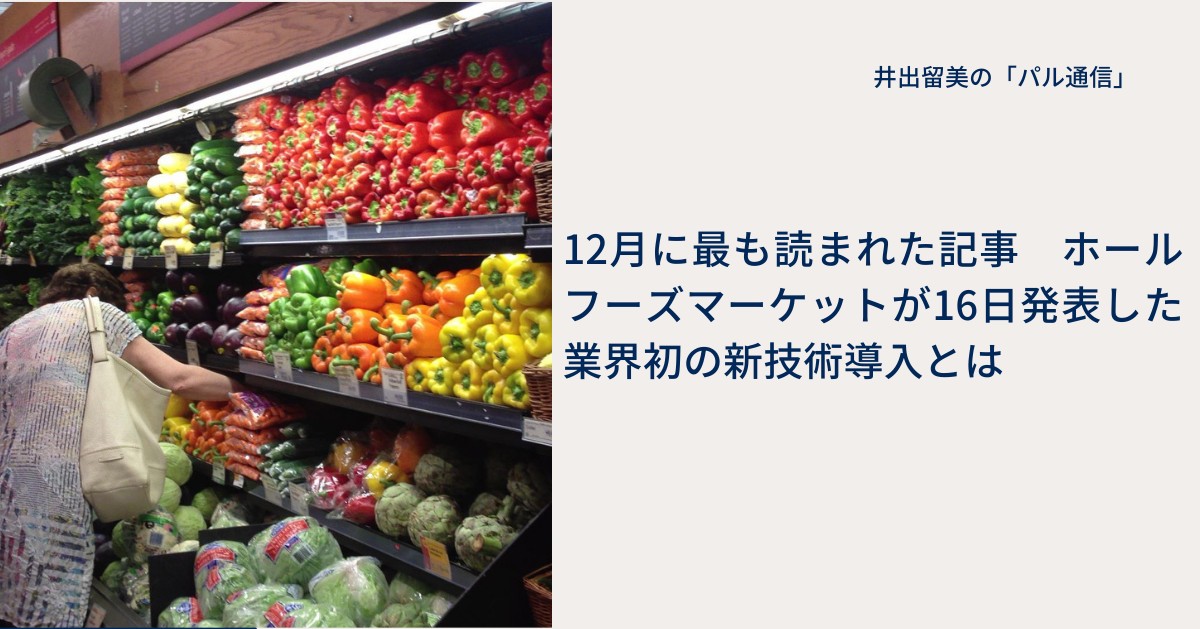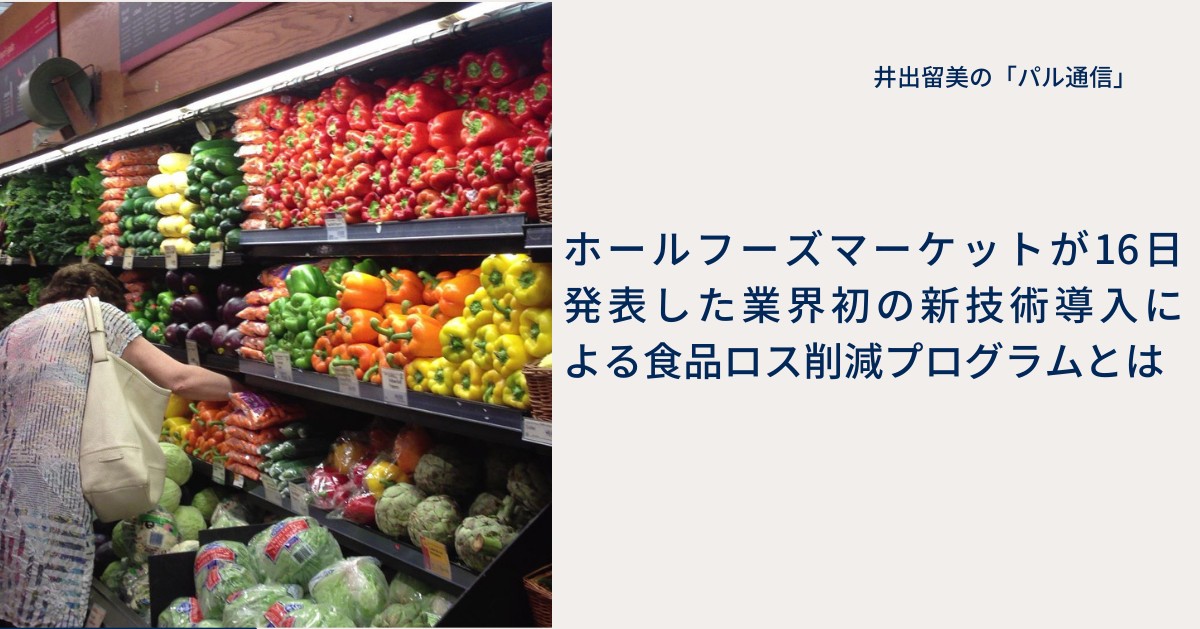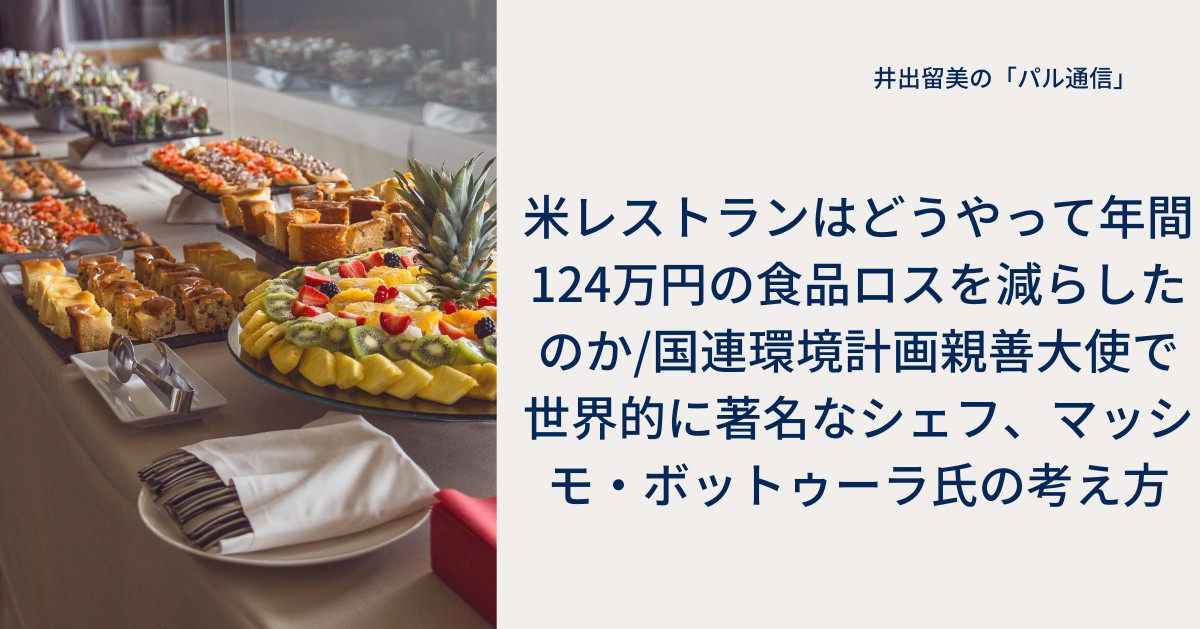アップサイクル「リサイクルとどう違う?」日本や海外の9つの事例
こんにちは。ニュースレター「パル通信」にご登録いただき、食品ロス削減やサステイナビリティの活動を支援いただいてありがとうございます。このニュースレターは、サポートメンバー(有料読者)と無料読者あわせて1,800名以上の方にお読みいただいています。特にサポートメンバーの方には定額をサポートいただいているおかげで、海外の記事購入や取材、渡航費に充てることができております。感謝申し上げます。
ニュースレター「パル通信」180号ではアップサイクルに関する国内外の事例を紹介します。2024年4月17日に配信した記事のアップサイクルの事例に関心を持つ方が非常に多かったので、ほかに国内外でどのような事例があるか、9つの事例についてご紹介します。
「アップサイクル」とは?
米国環境保護庁(EPA)が2023年10月に発表した報告書(1)によると、食品を「アップサイクル」することは、食品ロスを減らす上で、環境に対して最も負荷をかけない3つの方法のうちの1つ、とあります。
では、「アップサイクル」とは何でしょうか。
アップサイクルとは、本来、捨てられる運命にあったものに手を加えて、新たな価値を生み出したものです。水産庁の会議では、「アップサイクル」のことを「創造的再利用」という言葉で説明していました。アップサイクル食品協会(2)によれば、アップサイクル食品は、誰でも簡単に食品の廃棄を防ぐことができます。余った食品から新しい高品質の製品を作り出すことで、食品ロスを防止し、減らすことができます。
「リサイクル」とはどう違うの?
では、アップサイクルとリサイクルとの違いは何でしょうか。
リサイクルは、対象物をいったん資源に戻してから加工しますが、アップサイクルは対象物を資源に戻しません。対象物をそのまま生かした形で、元のものに付加価値をつけます。
たとえば、古紙を溶かして再生紙にする、牛乳パックを溶かして再生しトイレットペーパーにするのはリサイクルです。どちらもいったん資源に戻しています。
一方、古紙やチラシをそのまま折って簡易性のごみ箱を作る、牛乳パックをそのまま切って千代紙を貼って筆立てやプランターにする、というのはアップサイクルです。どちらも対象物を資源に戻すことなく、そのままを生かして付加価値をつけています。
朝日新聞SDGsACTION!の記事(3)では、わかりやすく表でその違いを説明しています。
では、具体的な事例として、どのようなものがあるのでしょうか。
1、りんご乙女(日本、マツザワ)
その一つが、長野県の食品メーカー、マツザワが作っている「りんご乙女」です。日本のリンゴ農家は、実を大きく実らせるため、ピンポン玉ぐらいの大きさの状態のときに、実の90%程度を下に落とします。これが「摘果(てきか)」です。

摘果されたリンゴ(もりやま園より提供)
その後は、葉っぱを取り(葉とり)、太陽の光をまんべんなく実にあてて、むらなく真っ赤なリンゴをつくります。
マツザワでは、この摘果リンゴを使って、リンゴの薄焼き煎餅のようなお土産菓子「りんご乙女」を作りました。リンゴ農家では、夏の時期、7月・8月は収入がなかったのですが、摘果リンゴを集めてマツザワへ売ることで、月に20万円から30万円の収入増につながりました(4)。取材に行ったとき、リンゴ農家さんがとても喜んでいらっしゃったのが印象的でした。

りんご乙女(マツザワ提供)
2、テキカカシードル(日本、もりやま園)
日本で最も古いリンゴ園、もりやま園。青森県弘前市にあります。ここでも、捨てていた摘果を捨てずに集めて、リンゴのお酒、シードルを作りました。
「摘果」は、普通のリンゴと比べて、ポリフェノールという抗酸化物質が10倍、多く含まれているそうです。味が酸っぱい。だから、なかなか製品化までこぎつけず、3年かかったそうです(5)。

もりやま園のテキカカシードル(筆者撮影)
もりやま園の森山聡彦(としひこ)さんは、さらに、日本の農業の労働生産性を向上させたいと考え、自身のリンゴ園でおこなっている労働時間をすべて計測しました。その結果、全労働時間のうち75%を「捨てる作業」に使っていることがわかりました。主に3つ。1つは摘果。2つめは枝の剪定。3つめは「葉とり」(まんべんなく赤くするため、葉っぱを取る作業)。でも、海外の農家を見れば、誰も「葉とり」はやっていない。そこでもりやま園では葉とりをやめました。論文では、葉をとらないほうが味が良いという結果も出ています(地域によって異なる)。

もりやま園提供写真
3、パルプ・チップス(米国、パルプパントリー)
南カリフォルニア大学で環境科学を学んでいたケイトリン・モゲンタールは、友達がニンジンをジュースにしているのを見て、繊維(パルプ)の部分が残って食品ロスとして廃棄されるのに気がつきました。そこでロサンゼルスのジュース店から出る繊維がどうなるかを調べたところ、そのほとんどが埋立地に送られ、二酸化炭素よりも温室効果の高いメタンガスを排出することを知りました。
そこで、コールドプレスジュールの残りの繊維から作るパルプ(繊維)チップスの会社、パルプ・パントリーを立ち上げたのです(6)。今では、Whole Foods Marketなどを含む米国西海岸の、およそ600店舗でその製品が販売されています。
なぜチップスの形状にしたのか。モーゲンタールは、ガーディアン紙の取材に「10人中、9人は、毎日食べていない野菜や果物、食物繊維などを、これなら手軽に摂取できるから」と語っています(7)。彼女はジュース製造企業から一度に10,000ポンド(4,536kg)の繊維を回収しています。
4、スペア・トニック(米国、スペア・フード)
米国のスペア・フードは、アダム・ケイ(Adam Kaye)とジェレミー・ケイ(Jeremy Keye)の兄弟が設立した食品会社です(8)。米国ニューヨーク州では、毎年10億ポンド以上のホエイ(乳清、ヨーグルトの表面に出てくる水分のこと)が廃棄されています。そこで、シェフのアダム・ケイは、そのホエイを活かし、気候変動に配慮した食品を提供しようと考えたのです。
製品の一つが「スペア・トニック」。ギリシャヨーグルトをつくる過程でできる新鮮なホエイを使った飲料です(下記写真、左)。また「スペア・スターター」(下記写真、中)は、外食産業向けに、ソースやシチュー、タコスに使える6種類の野菜をブレンドした製品です。2024年下旬には、余剰野菜30%を使ったブレンドビーフバーガー、「スペア・バーガー」を発売予定です(下記写真、右)。

5、トマト・バジル・ソース(米国、マトリアーク・フーズ)
マトリアーク・フーズ(9)のCEO、アンナ・ハモンド(Anna Hammond)は、新鮮な農産物が無駄になってしまっており、米国では食料の38%が廃棄されている現状を変えようと思い、2023年、余剰トマトを使ったパスタソースを発売しました。公式サイトには「ソースが気候変動の解決策なのか?」との問いが投げかけられ、「そうかもしれない(It just might be)」と書かれています。以前の記事でもご紹介した会社です。

6、リニューアル・ミル(米国、Renewal Mill)
リニューアル・ミル(10)は、植物性食品を作るとき、製造過程で取り除かれる天然のタンパク質と食物繊維を原料にして、クッキーミックスやブラウニーミックスなど、焼き菓子の素などを製造しています。
7、FAVES: クライメート・キャンディ(米国、Climate Candy)
クライメート・キャンディ(Climate Candy)(11)、その名も「気候飴」!商品名は「FAVES」。
規格外、見栄えのよくない農産物から作られた製品です。果物の甘さを生かしています。規格外や見栄えのよくない農産物は、その25%が収穫されず、エネルギーの無駄遣いや気候変動にネガティブな影響を及ぼすことにつながるので、それを解決することを目指して開発されました。
原材料は下記です。
りんご果汁、りんごピューレ、かぼちゃピューレ、にんじんピューレ、さくらんぼピューレ、いちごピューレ、さつまいもパウダー、濃縮果汁(にんじん、ビートルート、さくらんぼ、オレンジ、レモン、黒にんじん)、米粉、ペクチン、天然香料
8、アップサイクルド・フーズ(米国、Upcycled Foods)
アップサイクルド・フーズ(12)は、醸造過程で得られた発芽古代穀物を使い、アップサイクルする特許技術を得ている会社です。ReGrained SuperGrainという製品は、焼き菓子やスナック、ソース、飲料などに使うことができます。

アップサイクルド・フーズの公式サイトより
9、リンド(米国、Rind)
リンド(Rind)の創始者はマット・ワイス(Matt Weiss)です。彼女の曾祖母、ヘレン・サイトナー(Helen Seitner)は、1920年代、当時まだ珍しかった自然食品の店を開きました。いわばパイオニアです。
曾祖母のヘレンは、農産物や種、ナッツなど。精白した小麦粉を扱わず、ビタミンやミネラル、食物繊維の豊富な全粒粉だけを扱っていました。ジュースを作るために100ポンドのニンジン袋を購入し、野菜や果物は、根も皮も種も茎も丸ごと使っていました。何も無駄にしない、ということです。彼女が100歳近くまで元気で生きる姿を見たマット・ワイスは、曾祖母に敬意を表し、本格的で健康的なスナック、リンド(Rind)を提供することに決めたのです。
以上、日本と海外の9つの事例を紹介しました。海外事例は米国のみでしたが、エストニア、チリ、オーストラリア、カナダ、デンマークの記事も以前紹介しましたので、こちらの記事(14)もあわせてご覧ください。
専門家「消費者が食品ロスを意識するきっかけに」
英国ガーディアン紙の記事(7)によれば、食品ロスの専門家たちは、これらアップサイクルの新興企業だけでは食品ロスの危機を解決できない、と述べているそうです。なぜなら廃棄の半分近くは家庭で発生しているからです。次いで農場、製造業、外食産業、小売業と続くので、家庭からのロスが半分を占める以上、事業者の努力だけでは確かに解決することはできません。
オハイオ州立大学の食品ロスコラボレーションの責任者、ブライアン・ロー(Brian Roe)氏(15)は、ガーディアン紙の取材に対し「食品ロスに対する特効薬は一つもない。どんなタイミングでも、この問題に対して挑んでいくことは素晴らしい」「アップサイクルのブランドは、消費者が食品ロス問題を考え、意識するきっかけになります」と好意的に話しています。
ブライアン・ロー氏は、2005年に生ごみの埋め立てを禁止した韓国を「グローバルで最も興味深い事例」とガーディアン紙に挙げています。ごみの分別が義務付けられ、年間20ドル程度の税金が課せられたことで、一般市民が無駄にしていた量を20%減らすことにつながりました。
食品ロスの専門家は、米国が食品ロスに対処する方法を変えるためには、環境政策への取り組み、サプライチェーンの最適化、教育、食品のレスキュー(リユース)とリサイクルの強化、集団行動をミックスしておこなう必要があると述べています。
参考資料
10)Renewal Mill
13)Rind
今日の書籍
新卒で大手書店チェーンリブロに入社し、福岡、広島、名古屋と異動、池袋本店マネージャーを務めた著者が閉店で退職し、独立して自分の本屋、Title(タイトル:東京都杉並区)を立ち上げるまでのストーリー。長野県東御市のブックカフェ「問(Tou)」で見つけて購入しました。単行本と文庫と両方あったのですが、文庫は「増補版」になっていたのでこちらを選択。自分が4年間住んでいた久留米の話や、転勤の話、独立するとほとんど休みがなくなる話、などなど、自分の経験になぞらえながら一気に読みました。本が好きな人はもちろん、いずれ独立したい人、すでに独立している人にもおすすめです。もうすぐ新著も出るそうですよ。

新刊が出ます。『熱風』連載を改題の上加筆修正。自分で言うのも何ですが、これまで出した本の中ではもっとも「面白い」本になりました。この社会で自分らしく生きたい人には、一つの灯りになると思います。→
今日の映画
監督:白石和彌
出演:草彅剛、清原果耶ほか
古典落語の演目「柳田格之進」をもとにして書かれた小説『碁盤斬り 柳田格之進異聞』(加藤正人著、文春文庫)を描いた映画です。あらすじも登場人物も知らずに観に行きましたが、見応えのある映画でした。中でも注目は國村隼さん。誰にも代わりはできない、この人にしかできない演技があるな...と思うと、自分も仕事上で、誰にも代わりのできない何かを生み出さなくては...と思います。國村さんは、草彅剛さんと碁を打つシーンが多いのですが、裏話によれば、二人とも碁のルールはさっぱりわかっていなかったそう。小泉今日子さんは、廓(くるわ・遊郭)の女将の役どころ。やさぐれた役がピッタリはまっています。舞台挨拶では、この役のことを「世の中の表も裏も見てきた、貫禄ある女性」と語っています。映画では本当に「貫禄ある女性」として映っていて、意図してこう撮ったのかもしれませんが、女性として、もうすこし綺麗に撮ってあげてもいいのにな、とは思いました。映画後半、斎藤工さんと草彅剛さんとの対決シーンも見どころです。
あらすじ(公式サイトより):浪人・柳田格之進は、身に覚えのない罪をきせられた上に妻も喪い、故郷の彦根藩を追われ、娘の絹とふたり、江戸の貧乏長屋で暮らしている。しかし、かねてから嗜む囲碁にもその実直な人柄があらわれ、嘘偽りのない勝負を心がけている。ある日、旧知の藩士により、悲劇の冤罪事件の真相を知らされた格之進と絹は、復讐を決意する。絹は仇討ち決行のために、自らが犠牲になる道を選び・・・父と娘の誇りをかけた闘いが始まる!
編集後記
今週は、義母の誕生日祝いで長野県東御市(とうみし)へ行ってきました。奈良の蚊帳(かや)を使ったピンクの布巾を買ってきました。複数店舗で販売されているお米の精米時期に関する情報を調べてくださった方の中から抽選で1名さまにプレゼントしたいと思っています。このニュースレターに返信してください!今日はこのあと神奈川県鎌倉市で開催されるごみフェスに行ってきます。5月28日は農林水産省ASEAN事業の一環で、フィリピン・ビサヤ大学へ、食品ロスと気候変動の関係について講演。6月5-7日は、ボランティアで監事をつとめているおてらおやつクラブの総会で奈良の東大寺へ行ってきます。
明日5月26日(日)まで、おてらおやつクラブと京都のチャリティブランドJAMMIN(ジャミン)とのコラボで、オリジナルTシャツやトートバッグの販売があります。販売価格の20%が活動に寄付されます。私も買いました!今回でコラボは3回目です。6月8日は、広報を手伝っている東京大学農学部の公開セミナー「海と農学」が開催されます。キャンパスとオンラインの両方(ハイブリッド)で開催ですので、興味のある方はご登録ください。私は午後から弥生キャンパスにいる予定です。
5月も残り一週間。もうすぐ一年の半分が終わってしまうなんて!一日一日を大切にしたいです。
2024年5月25日
井出留美
・サステナビリティ情報も配信中
・過去の記事も読み放題
・毎週届き、いつでも配信停止可能
・読みやすいデザイン
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績