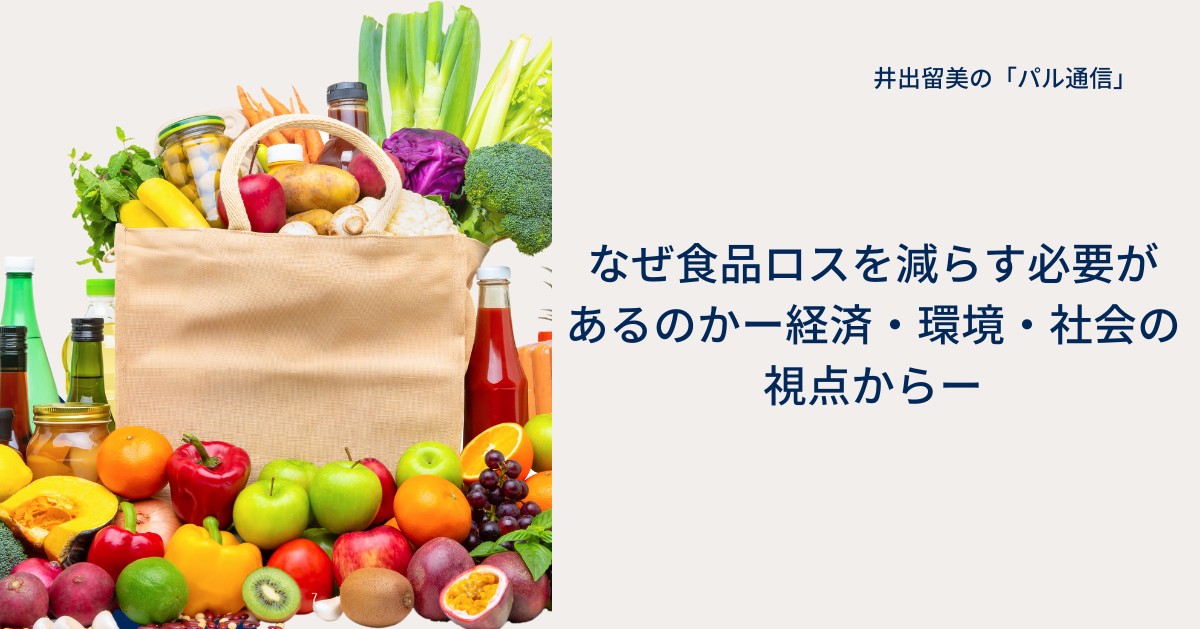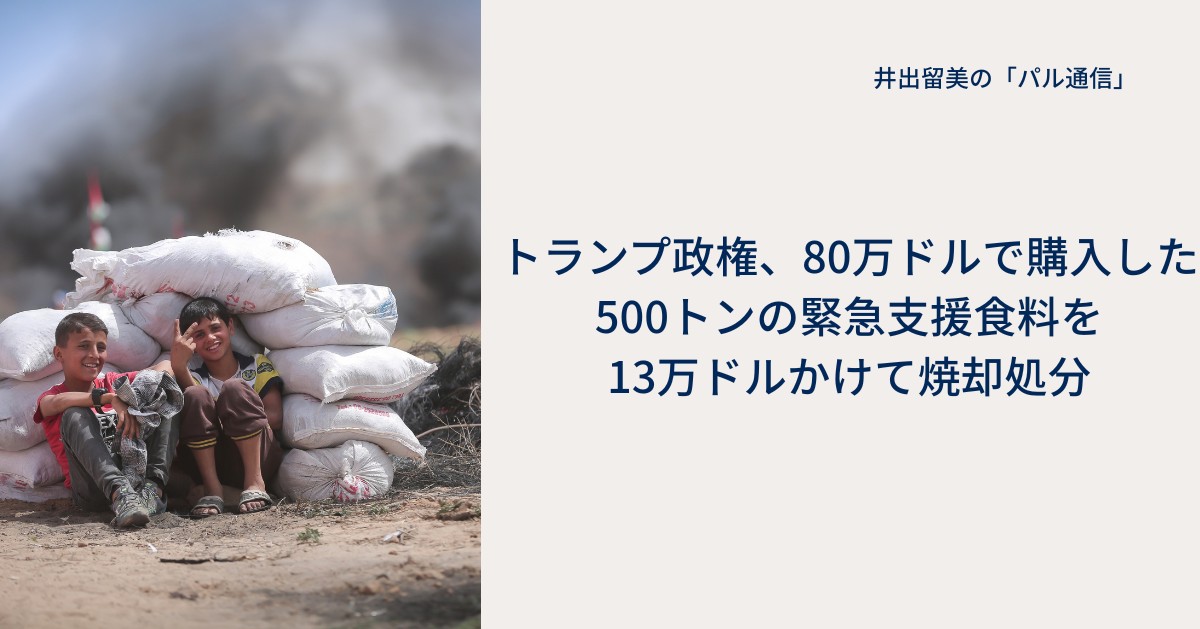どうすれば著書を出版できるのか 10年間で12冊出版したある著者の事例
こんにちは。ニュースレター「パル通信」にご登録いただき、ありがとうございます。あたたかい日が続いたかと思ったら、また気温が下がるようですね。花粉も飛んできていて、花粉対策や風邪予防など、いろいろ気をつかう季節になってきました。
ニュースレター「パル通信」235号では、どうすれば著書を出版できるのか、どのような経緯で本を出してきたのか、直接的な答えにはならないかもしれませんが、2014年からこれまで、約10年間で12冊の単著を出版してきた経緯を一つの事例としてお話します。読者の方から質問がありましたので、それを記事でお答えすることにします。
今後とも、ご質問がありましたら、記事で答えられる内容でしたら記事に書いていきたいと思いますので、リクエストをお待ちしております。なお、コメントがある方は、記事の最後にあるコメント機能をお使いください。書き手にのみ返信する方法と、読者全員に返信する方法があります。
食品企業時代に企画数件、実現に至らず
食品企業に勤めていた14年5ヶ月の間、特に一人で広報と栄養、社会貢献の責任者をまかされていたとき、2回か3回ほど、出版社や編集者から「本を書きませんか」と声をかけてもらったことがありました。全部は覚えていないのですが、はっきり覚えているのは、当時、全社員に配信していた「広報室ニュースレター」の経験をもとにした書籍です。
2000年ごろから2011年7月で退職するまでの間、全部で1305号の「広報室ニュースレター」を社内に配信していました。といっても、当時つとめていた会社では、マーケティングと営業が主力であり、たった一人の広報には予算がほとんどありません。そこで、A4一枚のpdfにまとめた「広報室ニュースレター」を、社長以下、全社員にメールで配信していました。内容は、マスメディアにとりあげられた自社製品のこと、競合企業のこと、自分が参加したシンポジウムやセミナーの内容、おすすめの書籍、食品業界のことなどさまざまです。発信していくうちに、全国の社員からも情報をもらえるようになり、双方向の関係性ができてきました。
そのことを、経団連の全国社内広報大会で発表したからか、ある出版社から「A4一枚にまとめる」といった内容の企画をいただいたことがありました。おそらく、編集者が考えてくださったのですが、社内の編集会議か営業会議に通らなかったのだと思います。2009年ぐらいだったでしょうか。
元NHKの方の声がけで2011年に共著を出版
その後、元NHKの方や、日本トイレ研究所の声がけで「カッサンドラの会」というのが立ち上がりました。子どもの睡眠、食、運動、排便、すべてを大切に考えようということで、医師や栄養士、大学教員など、それぞれの分野の仲間が集まり、シンポジウムを開いたりしていました。私は「食」の担当です。
その6名の中に、出版経験のある、元NHKの方がいらっしゃり、「せっかくだから、みんなで本を出そう」ということになりました。企画したあと、東日本大震災が発生、予定よりもだいぶ遅れたのですが、2011年10月、『四快のすすめ』(新曜社)という共著(1)が誕生しました。出版経験者がいることで、その人が出版社との折衝などをやってくれたので、経験のない私や他のメンバーは、その人におまかせしている状態でした。
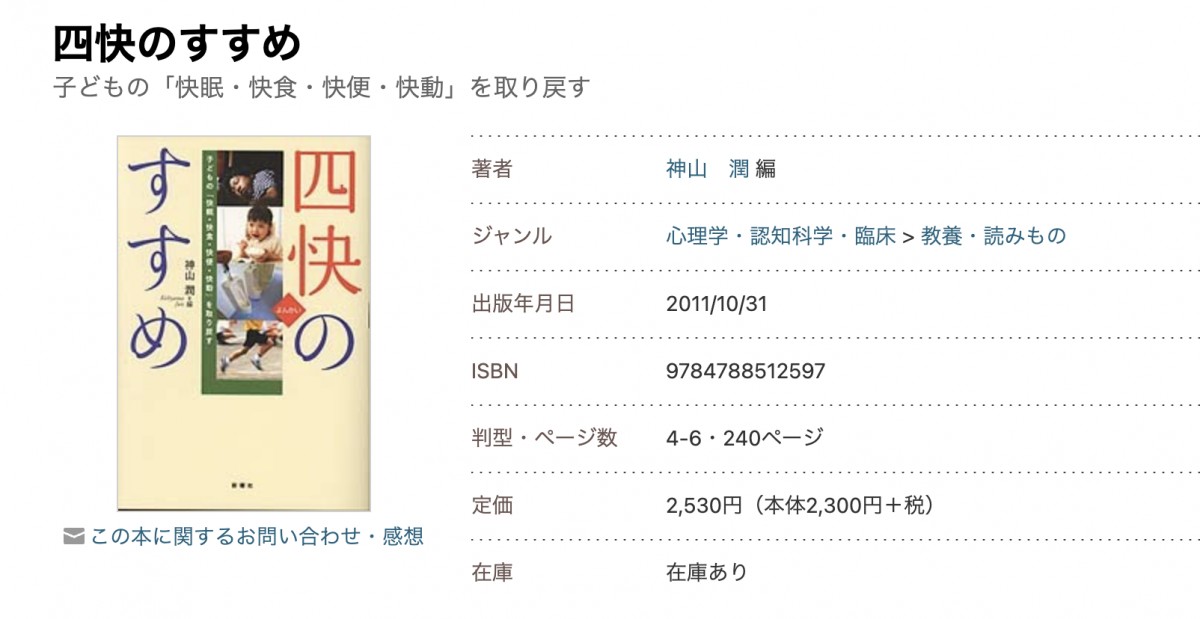
放送作家「やせてはいけないっていう本はどうだろう?」
東日本大震災の日が私の誕生日です。食料支援をはじめたこと、震災時に食料が必要なところに届かなかったこと、食品ロスの問題を知り、2011年に食品企業を辞めました。それまで自社製品を寄付していたフードバンクから「井出さん、会社辞めたのならうちの広報をやって」と言われ、2011年秋から3年間、フードバンクの広報責任者をつとめていました。
すでに食品企業時代、社会人で大学院に通い、栄養学の博士号を取得していたのですが、さらに大学院に入学し、農学生命科学研究科に籍を置くことになりました。その大学院の入学式で、放送作家の方が同席してくださり、「やせてはいけないっていう本を考えているんだけどどうだろう」と、本の執筆を声がけされました。その頃、痩せすぎの若年女性が健康上の大きな社会問題になっており、痩せすぎのモデルは採用されない、といったことも起きていたのです。私も、10代以降、体重が40kg台から60kg台まで大きく揺れ動く経験をしていました。
そこで出すことになったのが『一生太らない生き方』(ぴあ)という本(2)。このときも、放送作家のわぐりたかしさんが出版経験を持っていたので、お願いして出した、さらにライターの方にもサポートいただいた形でした。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績