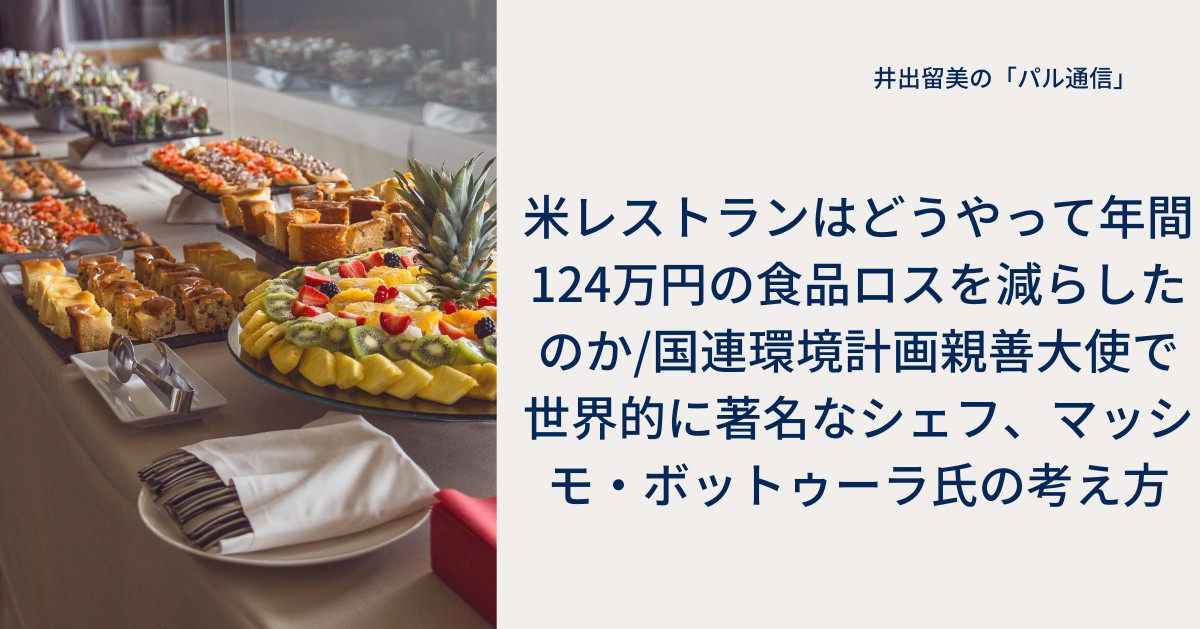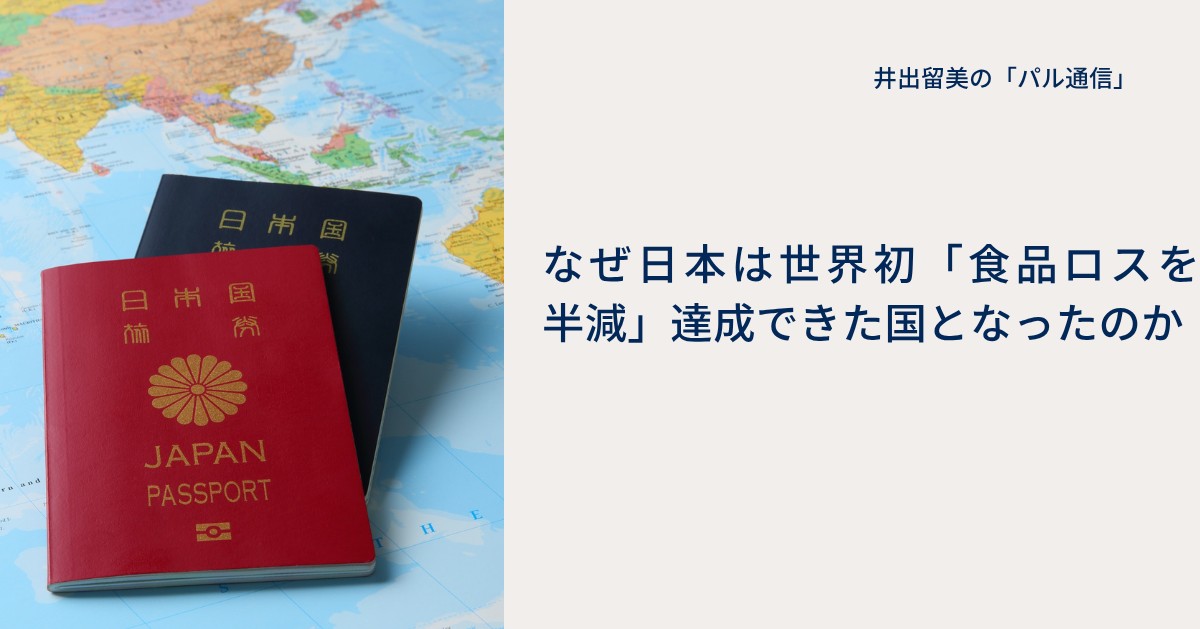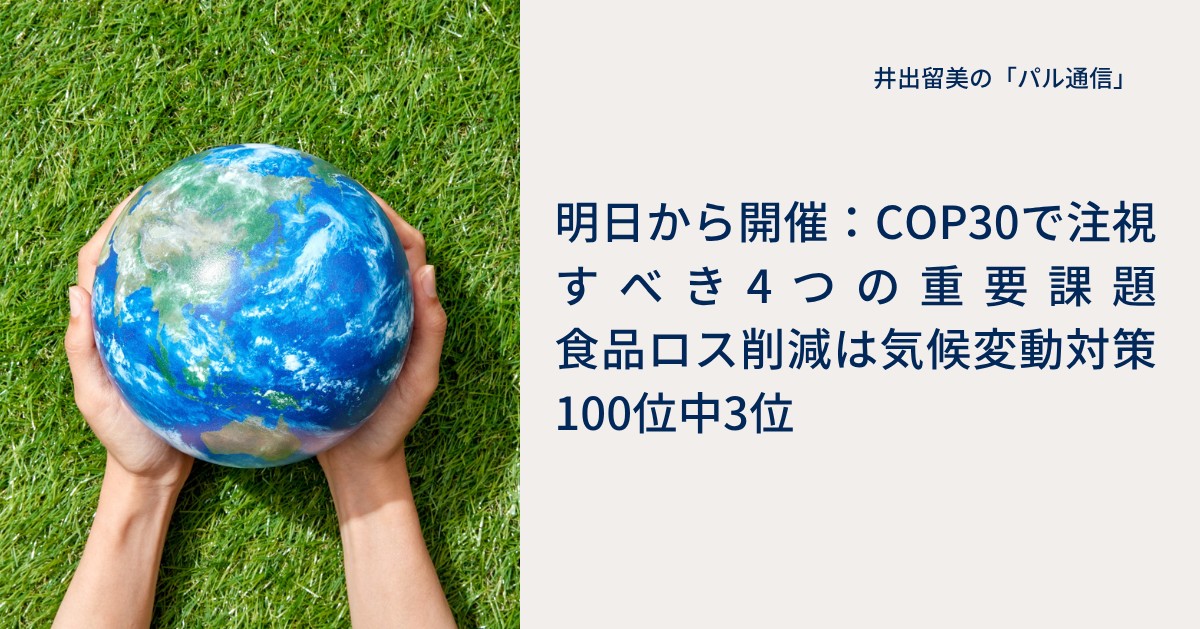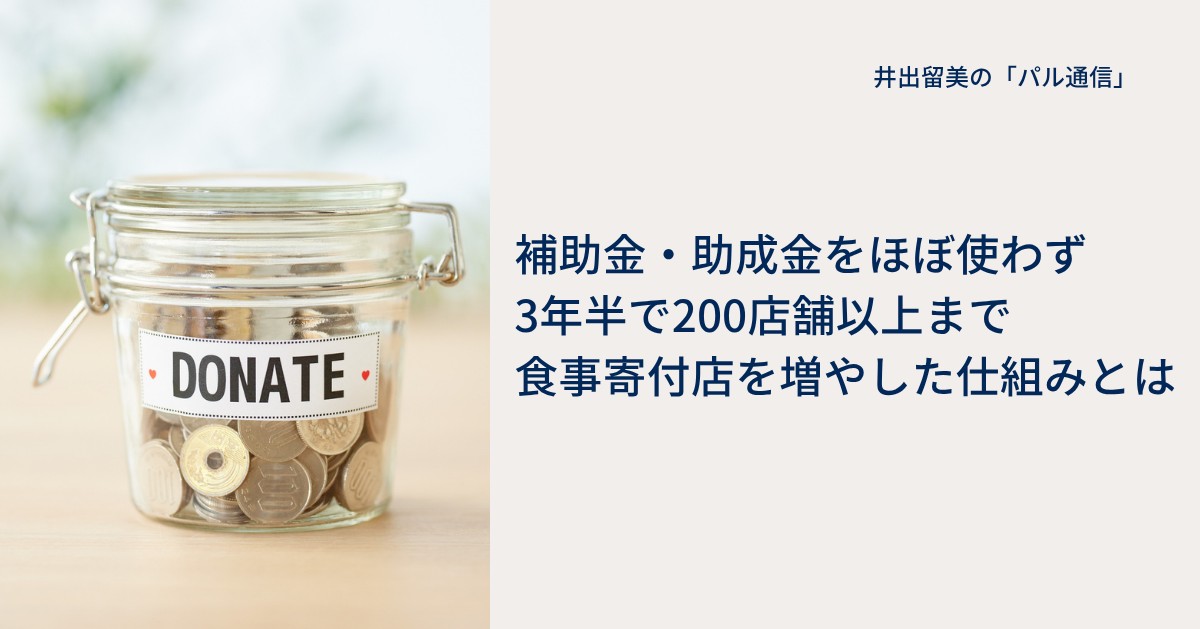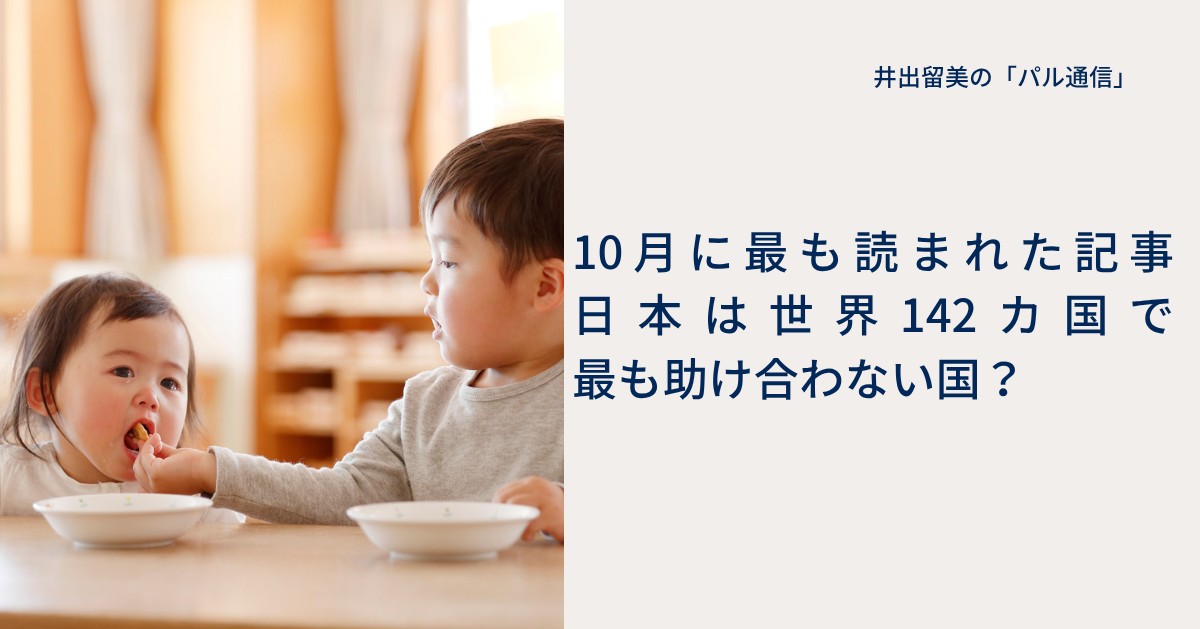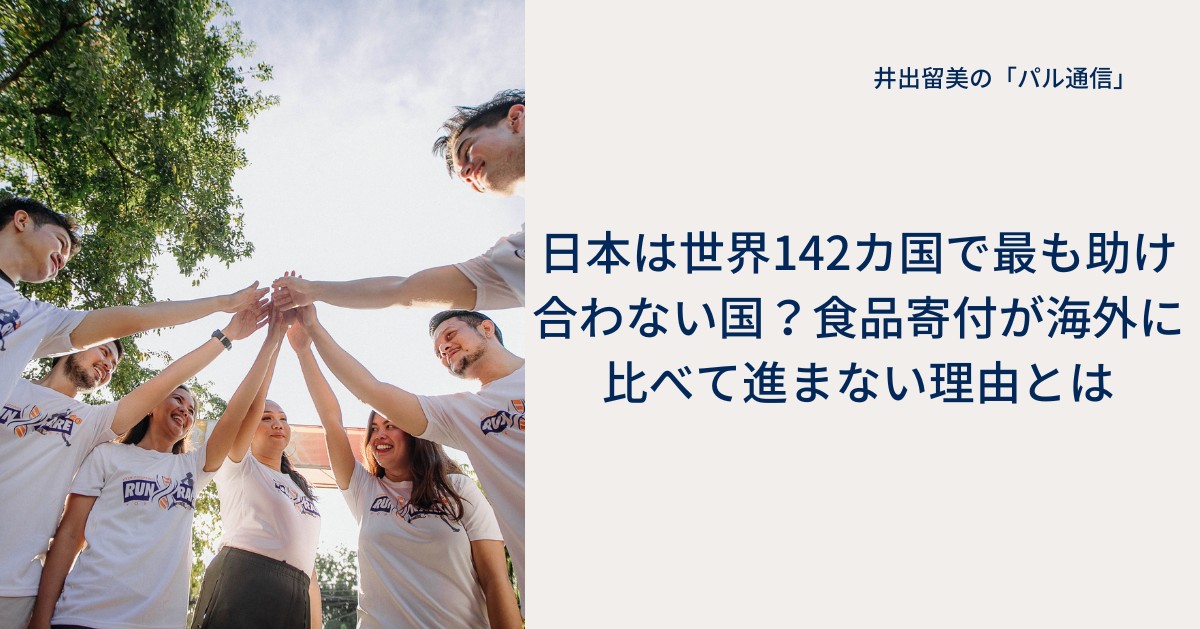食品ロスを生み出す「3分の1ルール」など商慣習に独占禁止法違反の恐れ 公正取引委員会
こんにちは。ニュースレター「パル通信」にご登録いただき、ありがとうございます。5月も半ばとなりましたね。
ニュースレター「パル通信」247号では、2025年5月12日、公正取引委員会が発表した「3分の1ルールなど、食品業界の商慣習の一部に独占禁止法違反の恐れがある」について解説します。
記事をお読みいただいてのコメントがある方は、記事末尾にあるコメント返信機能をお使いください。書き手にのみ返信する方法と、読者全員に返信する方法があります。
食品業界の商慣習、3分の1ルールなどの一部が「独占禁止法違反の恐れ」と公取
食品業界には、法律ではないものの、それに従わないと商売が成り立たないルールがあります。代表的なものが「3分の1ルール」です。そのほか、「欠品ペナルティ」や「日付逆転品の納品禁止」などがあります。その多くは、小売がメーカーに課すものです。
このような商慣習の一部が、公正取引委員会の定める独占禁止法に違反する恐れがあることが、公正取引委員会によって、2025年5月12日に発表されました(1)(2)(3)。「優越的地位の濫用」にあたる、というのです。
では、「3分の1ルール」や、それによって食品メーカーや小売店で起きる食品ロスについて、くわしく見ていきましょう。
3分の1ルールとは?
3分の1ルールとは、製造から賞味期限までの期間を3分の1ずつに区切り、最初の3分の1
を納品期限(納入期限)とし、次の3分の2を販売期限とするものです(4)。
3分の1ルールは誰が設定したのか?その理由とは
なぜ、製造から納品までを「3分の1」にするのでしょうか。
できるだけ「作りたて」、作ってから新鮮なうちに商品を納めるためです。
納品期限のあとに「3分の1」の販売期限を決めたのは、賞味期限ギリギリのものを売ると、「お客様」が自宅に持ち帰って食べる余裕がないからです。
ちなみにコンビニのおにぎりやカツ丼、サンドイッチなども、消費期限ギリギリまで売りません。販売期限は、消費期限が切れる1〜2時間前に設定されています(企業によって異なる)。
では、3分の1ルールは、いったい誰が決めたのでしょうか。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績