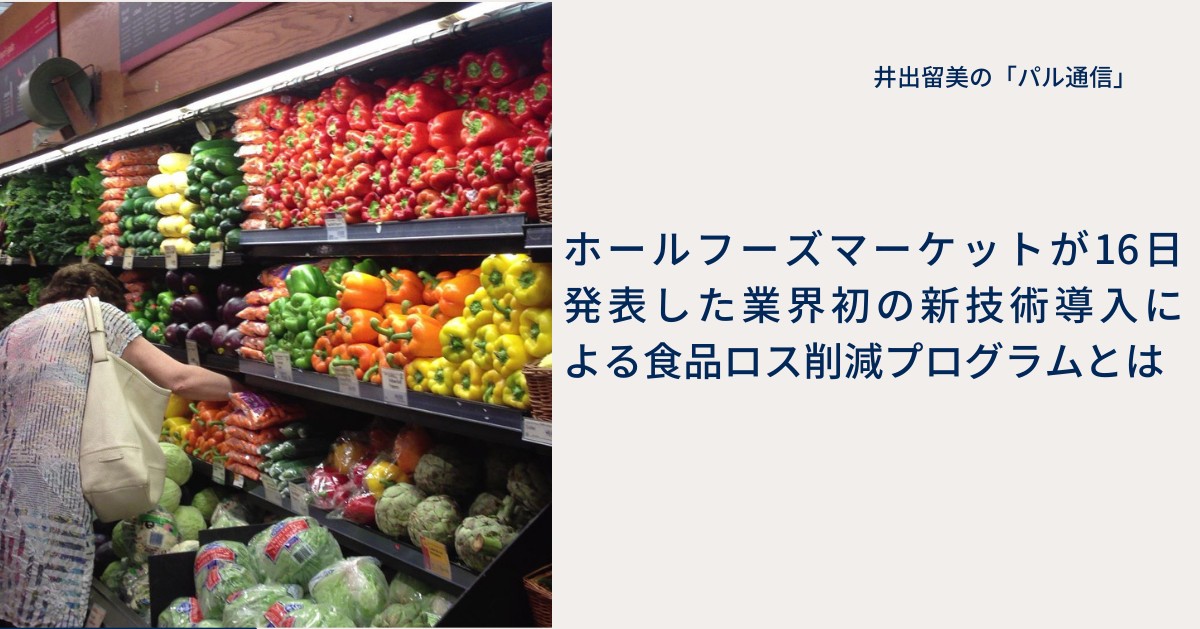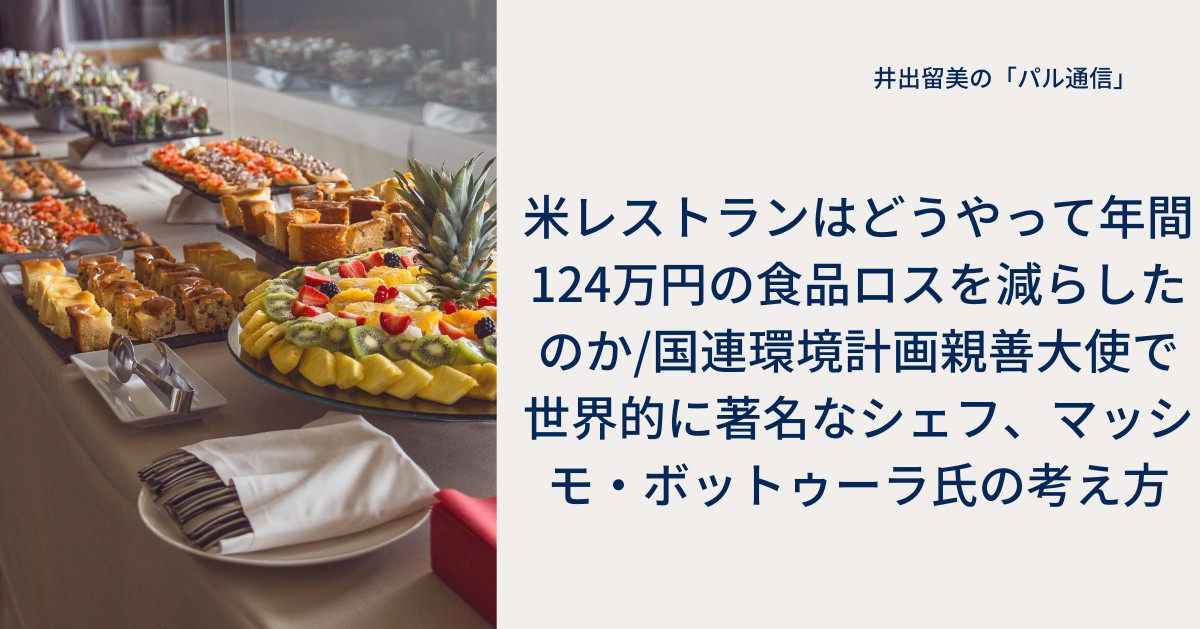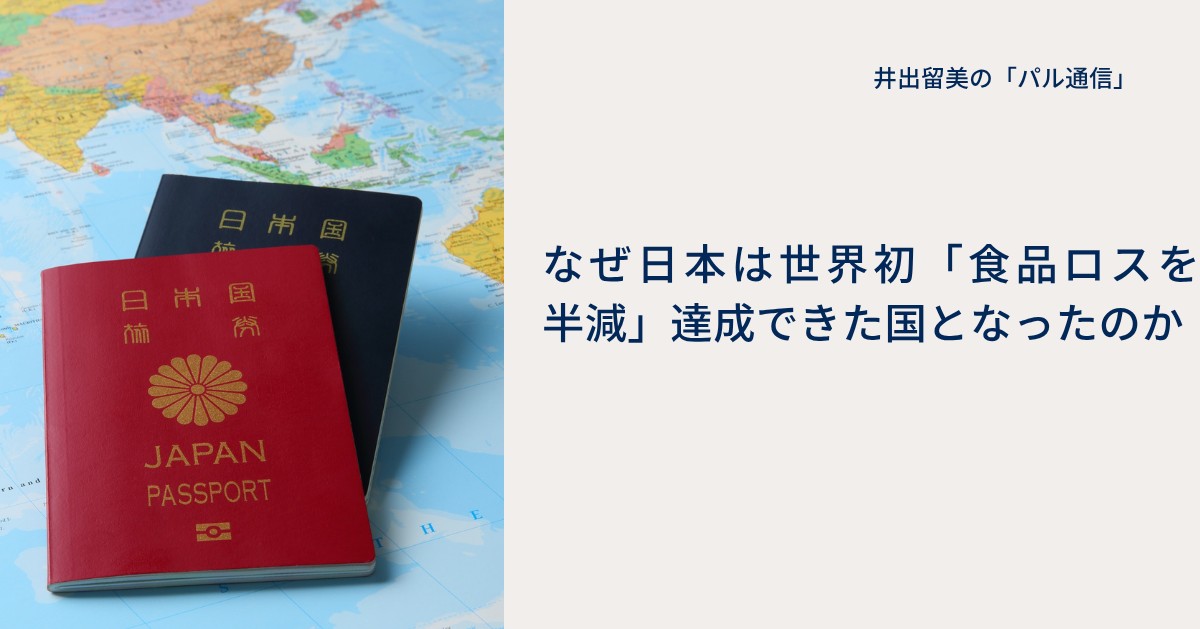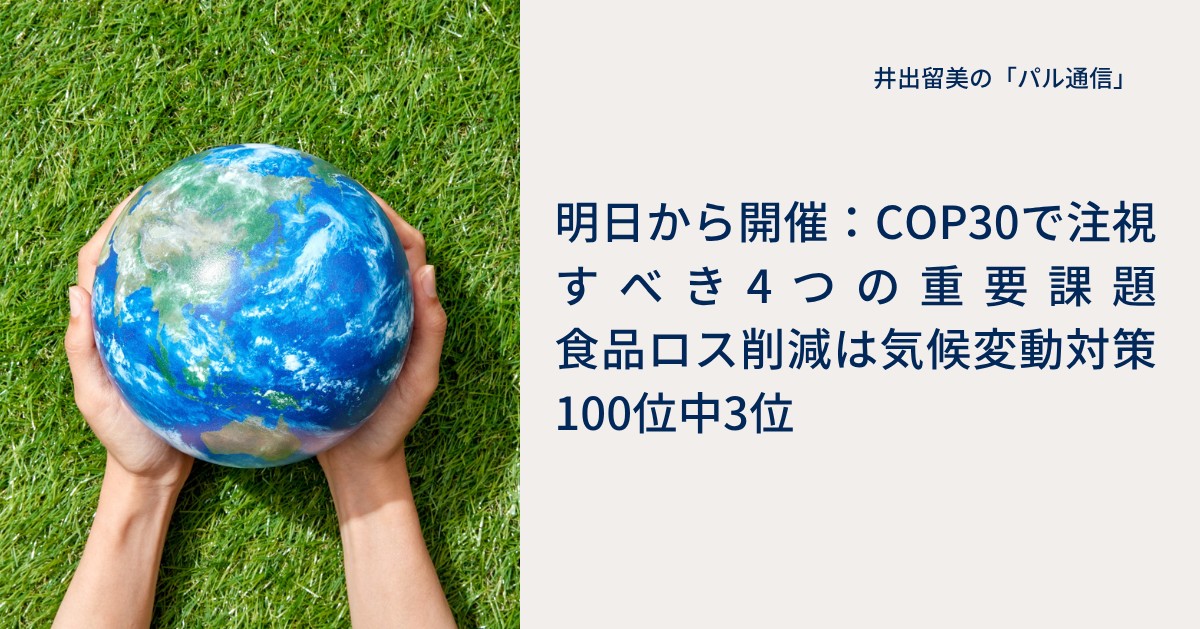なぜ生乳廃棄は続くのか?農水省の政策は付け焼き刃で他人ごと パル通信(106)
乳牛から搾られた「生乳」は、殺菌処理されて「牛乳」として出荷されていきます。せっかく絞った生乳が捨てられる、あるいは生乳を生産抑制しなければならない事態が起きています。絞った生乳を加工すれば済むのでは、という意見もあります。実際はどうなのでしょうか。
本記事は、途中まではどなたでもお読みいただけます(途中からはメールアドレス入力でお読みいただけます)。サポートメンバー(月額500円)のみなさまのおかげで、広く多くの方にお読みいただきたい記事を、このように無料でお届けすることができます。いつも、食品ロス削減や啓発に関する活動を支援していただき、感謝申し上げます。
この記事を書いた理由
酪農の周辺で起きていることに対し、疑問の声を呈する読者の方が複数いらっしゃったため。
この記事でわかること
「余った生乳はバターなどの加工食品にすれば捨てないで済むのか?」の問いに対する答え。
「余った生乳はバターにすれば廃棄せずに済むのに」乳業業界の回答とは
2021年末にも、生乳が余る事態が発生しました。その際、業界団体のJミルクに取材し、「余った生乳5000トンはバターにすれば廃棄せずに済むのに」乳業業界の回答とは?という記事を書きました。
乳業業界では、日頃から、牛乳の需要が多ければバターなどの製造量を減らし、牛乳の需要が減ると、バターの生産量を増やします。バターは、いわば生乳需給の調整弁の役割を果たしているのです。
でも、バターを作る過程では、脱脂粉乳も製造されます。
2021年は、全国の乳製品工場をフル稼働させていました。それでもなお、その製造能力を超えてしまうため、「牛乳を飲みましょう」と政府が呼びかける事態になったのです。
生乳を捨てるのではなく、保存のきくバターや加工食品にすれば捨てなくて済むのでは?
2023年現在、酪農に関する問い合わせが酪農家や消費者から多く寄せられているため、農林水産省は、公式サイト上で、Q&A方式にして回答しています。
「生乳を捨てずに、保存のきくバターや脱脂粉乳にすればよいのでは?」
これに対し、農林水産省は、次のような趣旨を回答しています。
「従来から、生乳が余る場合は、バターや脱脂粉乳の製造を増やしてきた。バターの需要は現在増えている。だが、脱脂粉乳は需要が低迷しており、在庫が過去最高に達してしまっている。これ以上、脱脂粉乳の在庫が積み上がると、乳業メーカーの経営が圧迫されてしまう。そこでやむをえず、生産者団体は、生乳生産を抑えてきている」
バターを製造すれば、必然的に、脱脂粉乳も製造されることになります。どちらも生乳よりは長く保ちますが、バターや脱脂粉乳も、「賞味期限」が設定され、さらにその前に販売期限などが設定されるので、バターや脱脂粉乳にしておけば万事OK、というわけにはいかないのです。
「余った脱脂粉乳を食料援助に使えばいいのでは?」という意見もあります。これに対して、農林水産省は「食料援助は相手国からの要請に基づいておこなわれるが、脱脂粉乳が欲しいという要請は、今のところ、ない」と、答えています。
「大量に輸入しているチーズを国内で作ればいいのでは?」
では、いま、大量に輸入しているチーズを国内で作ればよいのではないでしょうか。
これに対する農林水産省の回答は、次のような内容でした。
「輸入チーズは安い。輸入チーズの分を、国産チーズでまかなおうとすると、価格を1キロあたり20円下げないといけない。酪農家の生産コストが上がっている状況下で、それは難しい。そこで、価格を下げるのではなく、今の国産チーズにしっかり価格転嫁をしていく、品質やブランドで勝負する、という考え方になっている」

農林水産省YouTubeより
なぜ増産する方針だったのに減産するのか
そもそも、2014年にバター不足が生じたことが、乳牛を増やすきっかけとなりました。乳牛は、すぐに乳を出すわけではありません。何年も育てて、ようやく生乳を絞れるようになります。そこにコロナ禍が襲い、需要が下がってしまいました。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻によって、飼料価格の高騰が続いており、これが酪農家に打撃を与えました。そこで、いま、増産から減産に転じているのです。なぜでしょうか。
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績